>>戻る
|
|
 |
 |
|
レジオネラニューモフィラの電顕像 |
(1)レジオネラ属菌の歴史〜1976年、アメリカのホテルで発生!
1976年7月。ペンシルベニア州フィラデルフィアのホテルで開催された在郷軍人会(The Legion)において、
参加者やホテル宿泊者221人が原因不明の肺炎で次々に倒れ、うち29人が死亡するという惨事が起こり
ました。米国の疾病管理センターが行なった原因調査によって、この肺炎はこれまで報告のなかった未知
の細菌による集団肺炎であることが確認され、在郷軍人会(The Legion)にちなんでLegionella、肺を好む
という意味からpneumophilaと命名されました。
日本で多くのマスコミが取り上げるようになったのは、96年12月に家庭用の24時間風呂にこの菌が繁殖
することがわかり、旧通産省が業界に改善を求めたのが最初のきっかけです。したがって、このレジオネラ
属菌が発見されたのはかなり最近のことなのです。

(2)レジオネラ属菌とは?
 |
レジオネラ属菌は、自然界の土壌(地表から深さ10cmまでと言われる)と淡水(川や湖)
に生息するグラム陰性桿菌で、菌体の端に1本の鞭毛があり、運動性を持った細菌です。
レジオネラ属菌は、一般に25〜43℃で繁殖し、特に36℃前後がより繁殖に適しているた
め、冷却塔や加湿器、温泉や風呂の浴槽など人工の環境においても条件によっては異常
繁殖します。 |

(3)レジオネラ感染症とは?
レジオネラ感染症はレジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、乳幼児や高齢者、病人など抵抗力が低下し
ている人がかかりやすいレジオネラ肺炎(肺炎型)とポンティアック熱(非肺炎型)という2つの病型に大
別されます。
レジオネラ属菌は、一般に25〜43℃で繁殖し、特に36℃前後がより繁殖に適しているため、冷却塔や加
湿器、温泉や風呂の浴槽など人工の環境においても条件によっては異常繁殖します。
| 【症状】 |
高熱・咳・痰・頭痛・胸痛・筋肉痛・悪感・下痢・意識障害など |
| 【肺の状態】 |
肺炎・胸膜炎 |
| 【潜伏期間】 |
2〜10日(平均4〜5日) |
| 【発病率】 |
1〜6% |
| 【死亡率】 |
15〜30% |
感染しても発病することは少ないが、重症化した場合、多臓器不全を起こして発病後
1週間以内で死亡するケースもある。 |
| 【症状】 |
発熱・咳・頭痛・胸痛・筋肉痛・悪感・下痢・意識障害など |
| 【肺の状態】 |
胸膜炎 |
| 【潜伏期間】 |
38時間 |
| 【発病率】 |
95% |
| 【死亡率】 |
0% |
発病しても多くの場合自然に治ってしまう(自然治癒型)。対症療法のみで完治し、
死には至らないが治癒後も数ヶ月に渡って健忘症を示すことがある。 |
|
|

■浴槽は、清掃および消毒を定期的に行ない、清潔で衛生的に保つこと。
■清掃および消毒の頻度は、以下の通りにすること。
| ※ |
毎日完全換水型のものは、毎日清掃し、1月に1回以上消毒する。 |
| ※ |
連日使用型のものは、1週間に1回以上完全換水を行ない、消毒、清掃する。 |
|
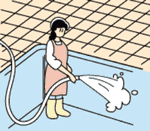 |
| 1: |
ろ過器の維持管理 |
| |
「公衆浴場における衛生管理等管理要領」では、ろ材の種類を問わず、ろ過装置自体がレジオネラ属菌の供給源とならないよう、消毒を1週間に1回以上実施すること。また、ろ過器は1週間に1回以上逆洗して汚れを排出することと定められています。 |
 |
 |
| 2: |
循環配管の維持管理 |
| |
循環配管の内側には、ネバネバした生物膜(バイオフィルム)が生成されやすく、レジオネラ属菌の温床となります。そのため、年1回程度は循環配管のバイオフィルムを除去し、消毒することが必要です。 |
 |
 |
| 3: |
消毒装置の維持管理 |
| |
薬液タンクの塩素系薬剤の量を確認し、補給を怠らないようにしなければなりません。
| ■ |
送液ポンプが正常に作動し、薬液の注入が行われていることを毎日確認する。 |
| ■ |
注入弁のノズルが詰まったり、空気をかんだりして送液が停止していないかを確認する。 |
| ■ |
市販品の次亜塩素酸ナトリウム溶液は、有効塩素濃度が12%で、そのまま使用するとノズルが詰まりやすいので、5〜10倍に希釈して使用する例が多い。 |
| ■ |
不純物の多い工業用のものは避け、日本水道協会規格品、食品添加物認定品あるいは医薬品として市販されている薬品を使用するとある程度目詰まりを防ぐことが可能。 |
| ■ |
薬剤注入弁は定期的に清掃を行ない、目詰まりを起こさないように管理する。 |
|
 |
 |
4:最近のレジオネラ感染症の事例
| 2000年6月 |
茨城県の福祉センターで45名発症、3名死亡 |
| 2002年1月 |
東京都板橋区の銭湯で1名死亡 |
| 2002年7月 |
宮崎県の温泉で295名発症、7名死亡。過去最大の被害 |
| 2002年8月 |
鹿児島県東郷町の温泉施設で9名発症、1名死亡 |
| 2003年1月 |
石川県山中町の温泉施設で1名死亡 |
| 2003年2月 |
岡山県岡山市の大学付属病院で1名死亡 |
|
5:レジオネラ感染症の感染経路
| レジオネラ感染症は、レジオネラ属菌を含んだ直径5μm以下のエアロゾル(霧状になった水)を吸入することにより感染します。レジオネラ属菌に汚染された循環式浴槽水、シャワー、ホテルのロビーなどの噴水、洗車、野菜への噴霧水のエアロゾルの吸入、浴槽水で溺れて汚染水を呼吸器に吸込んだ時などに感染・発症した事例が報告されています。汚染水の直接接触で外傷が化膿し、皮膚膿瘍になったり、温泉の水を毎日飲んで発症した事例もあります。ただし、患者との接触によって感染したという報告はありませんので、患者を隔離する必要はありません。 |

6:関係法規等に規定されている水質管理概要
レジオネラ感染症はレジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、乳幼児や高齢者、病人など抵抗力が低下
している人がかかりやすいレジオネラ肺炎(肺炎型)とポンティアック熱(非肺炎型)という2つの病型に大
別されます。
レジオネラ属菌は、一般に25〜43度で繁殖し、特に36度前後がより繁殖に適しているため、冷却塔や
加湿器、温泉や風呂の浴槽など人工の環境においても条件によっては異常繁殖します。
| (1) |
循環ろ過装置は、1時間当りで浴槽の容量以上のろ過能力を有すること。 |
| (2) |
循環ろ過装置を使用する場合は、ろ過の種類を問わず、ろ過装置自体がレジオネラ属菌の供給源とならないよう、消毒を1週間に1回以上実施すること。 |
| (3) |
浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤は、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を1日2時間以上0.2〜0.4mg/Lに保つことが望ましいこと。 |
| (4) |
温泉の泉質等のため塩素消毒ができない場合は、オゾン殺菌または紫外線殺菌により消毒を行なうこと。この場合、温泉の良質などに影響を与えない範囲で、塩素消毒を併用することが望ましいこと。 |
| (5) |
連日使用型循環式浴槽では、1週間に1回以上定期的に完全換水し、浴槽を消毒・清掃すること。 |
| (6) |
管理記録を3年以上保存すること。 |
|
|
|
|

